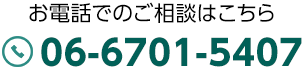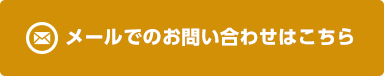2025年1月~12月
困った社員がいる場合は、指導記録を残そう その2(2025.8月号)
●困った社員がいる場合は、指導記録を残そう その2(2025.8月号)
前回からの続き
2.問題があると認識したら黙認せず、まず口頭で数回注意をすること
これは試用期間に限らず、本採用後であっても問題があると感じているなら、黙認してはいけません。特に問題社員は、自分が問題行動を起こしているという自己認識が低いことが多く、むしろ自分は問題なくちゃんとやっている、と思っていることがあるのです。
それを黙認していると、問題行動を間接的に肯定していることになり、後から注意すると「なぜ今まで言われなかったのに、今頃急に言われなくてはいけないのか」と反省するどころか、逆に不信感を買うか、反抗的な態度を返してくる可能性があります。
問題行動があると認識した段階で速やかに口頭注意をします。それで改善されれば苦労はしないのですが、一度や二度の注意で改善しないのが問題社員です。
改善しない場合は、次の段階へ進みます。次は文書による指導書を発行します。
【例】
●●殿
貴殿に対して、今まで口頭で何度も注意してきましたが、改善が見られないため、これまでの勤務及び業務遂行状況からみて改善をお願いしたい下記の事項について文書により指導しますので直ちに改善向上を求めます。
1.上司等の指示命令に従い誠実かつ忠実に勤務して下さい。
(勝手に自己流で判断しないで、十分指示等の意図を確かめてから取り掛かること。特に独自の見解で、独断で業務を遂行せず会社の意図に沿って業務を進めること。)
2.同僚杜員と協調融和し、また後輩に対し親切かつ適切に指導して下さい。
(上司の指示に合理的な理由なく反抗し、同僚杜員を批判したり不服を直接言うことによって職場の協調・一致を乱さないようにすること。他部署社員との打合せにあたっても円満で目的達成上有効な言動を行い、後輩又は部下社員に対し怒鳴ったり、大声で叱ったり、些細なことで文句を言ったりしないで、親切かつ適切な指導をすること。)
3.職場を無断で離脱することなく用件、行き先等を告げ連絡がとれるようにして下さい。
(勤務時間中しばしば無断で離席し、また社外に外出する等して連絡がとれないことがあるのできちんと離席手続を守ること。)
できれば2部作成して一部を交付し、もう一部に「内容を理解し改善に取り組みます」等と記した欄に直筆のサインをもらっておくことが望ましいですが、サインしない場合は手渡しだけでも構いません。●月●日に交付、署名を求めたが●●と言ってサインせず、などと直ぐに欄外に書いて記録しておいてください。万が一受け取り自体を拒否した場合も読み聞かせた上で、同様に受け取り拒否した事実を欄外に記録しておいてください。
注意指導書の様式には実に様々なものがあります。ケースバイケースで使い分けします。上記は一例に過ぎず、問題社員に手渡す文書を作るときはその都度弊社までご相談ください。
これでも改善されないときは、警告書を交付します。
【例】
貴殿には、令和●年●月●日付、「指導書」を交付して改善してほしい事項を明示しました。しかし貴殿は真摯に反省しないばかりか、反抗的な態度すら見られ、一向に改善されず、今回新たに●●という非違行為を起こしました。
今後、改善されず、または更に非違行為を行う場合は、当社は懲戒(解雇を含む)処分を含めて厳しく対処することとしますので、充分に注意してください。ここに社長名にて警告します。
これでも改善されなければ、けん責(始末書を取ること)や減給など軽い懲戒処分を行うことがあります。
ここまでを整理すると、
まず口頭で注意→指導書交付→警告書交付→(軽い懲戒処分) というような感じです。期間をどれくらい見るかは悩ましいところですが、改善の機会を付与する意味では最低3か月程度はかかるものと心得ておいた方がよいでしょう。これは一般的な流れであり、相手や行為態様により必ずしもこの通りであるとは限りません。
そして口頭注意から警告までの問題行動については、その都度日記のように時系列で記録しておくことです。後で思い出して書くのではなく、その日に記録しておきます。問題社員とともに過ごす機会の多い社員に記録をお願いすることもあります。
ここまでやってダメな場合はいよいよ最終段階へ進んでゆくことになります。最終段階とは退職勧奨か解雇を選択するということです。
(以下次号)
(文責 特定社会保険労務士 西村 聡)